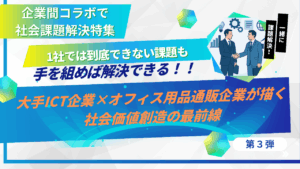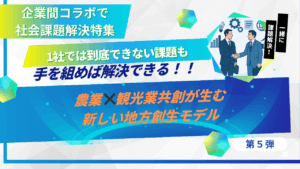食品ロス削減と就労支援をつなぐ協働 地方農産物直売所運営会社 ×地方障害者就労支援企画・運営会社
目次
- ◆はじめに
- ◆ 企業・団体紹介
- ◆コラボの背景・目的
- ◆具体的な取り組み内容
- ◆社会的影響
- ◆課題と今後の方向性
- ◆まとめ
- ◆お知らせ
◆はじめに
多くの社会課題の中でも「食品ロス」と「障害者の就労機会不足」は特に深刻なテーマとして注目されています。 農林水産省によると、日本の食品ロスは年間約500万トンを超えており、生産・流通・消費の各段階で大量の食品が廃棄されているのが現状です。
また、日本には働く意欲は高いけれど、就労機会に恵まれないまたは、仕事にやりがいが持てない障害者の方々がたくさん存在します。
この二つの課題を同時に解決しようという取り組みが、北関東のある地域で始まりました。農産物直売所などを運営する会社と障害者就労支援の企画・運営を手がける会社による協働です。
暫定では、この協働の背景や具体的な解決策、そして社会的視野について整理しながら、今後の可能性を考えていきます。
◆ 企業・団体紹介
🔼農産物直売所運営会社
農産物直売所などを運営している地域密着型の企業です。地産地消や地域の農業振興をコンセプトとし、新鮮な農産物の流通や観光客の食・体験コンテンツを提供しています。地域に集中した「食の魅力発信企業」として、農業と観光、食文化をつなぐ事業を展開しているのが特徴です。
農家から集められる農産物の中には品質に問題はないものの、規格外品として市場に出にくい野菜や果物がたくさんあります。この「もったいない」をどう生かすかが、長年の課題となっていました。
🔼障害者就労支援企画・運営会社
障害者就労支援施設の企画・運営を行っている企業です。 障害のある人が社会の現場で働き、自己実現できる場を作ることを使命としています。
「障害者の可能性を社会につなぐ」を理念に、福祉とビジネスを融合させた活動を展開しています。 障害者の労働は「保護の対象」ではなく「価値を生む創造的な仕事」と定義づけて、着実に取り組みを行っているが大きな特徴です。
◆コラボの背景・目的
両社のコラボレーションは、「食品ロス」と「障害者就労」という二つの社会課題が交差する場所から生まれました。
農産物直売所運営会社は、リアル店舗や地元農家とのネットワークを持ち、日々大量の農産物を仕入れています。 しかし、その中には市場価値が低いとされる規格外野菜や果物が発生してます。
一方、障害者就労支援企画・運営会社は福祉施設に通う障害のある人々に安定した仕事を提供したいと考えていました。 しかし、「作業の内容が単純で社会的意義を認識しにくい」という声もあり、利用者が誇りを持って取り組む仕事の拡大が必要とされていたのです。
農産物直売所運営会社が「使い切れない農産物を活用したい」と考えていたところに、障害者就労支援企画・運営会社が「利用者の就労機会を広げたい」と申し出ことがきっかけでした。 結果として、「規格外農産物を福祉施設で加工し、新しい商品として販売する」というプロジェクトが始動しました。
目的は単純に廃棄を減らすことだけではありません。「食品に新しい価値を見出すこと」「障害者が社会的役割を果たせるようにすること」、そして「地域経済を豊かにすること」が同時に追求されたのです。
◆具体的な取り組み内容
協働のプロジェクトでは、以下のような具体的な活動が展開されています。
🔼規格外農産物の仕入れと運搬
農産物直売所や提携農家から発生する規格外野菜・果物を回収します。 サイズが合わなかったり、色合いにムラがあったりといった理由で店頭に並びにくい商品が主です。
🔼福祉施設での加工作業
就労支援の利用者が、これらの農産物をジャム、ドライフルーツ、ピューレなどに加工します。洗浄・カット・加熱・パッケージングといった工程を分担し、利用者が自分の適性に合った役割で働ける体制を整えています。
🔼新商品の販売
出来上がった加工品は直売所や地元のイベント、オンラインショップなどで販売されます。「規格外から生まれた商品」というストーリー性もあり、消費者からは「環境にも福祉にも貢献できる商品」として好意的に受け入れられています。
🔼利用者の技術向上と評価
障害者就労支援企画・運営会社は、作業マニュアルや研修プログラムを準備し、利用者が食品加工のスキルを身につけるために仕組みを整えました。その結果、「自分の仕事が人の役に立っている」というやりがいや喜びが生まれ、働く人々は、一生懸命に取り組む良い環境ができました。このように、食品ロス削減と障害者就労支援がひとつの流れとしてつながる新しいビジネスモデルが構築されているのです。
◆社会的影響
この協働がもたらした社会的意義は大きく、以下のような成果が見られます。
🔼食品ロスの削減
規格外の農産物を新たな商品として活用することで、廃棄量が減少しています。
🔼障害者の働く誇りを生み出す
単純作業の提供にとどまらず、「商品づくり」という形で社会とつながることが、労働者の探求心につながりました。「自分の作ったジャムが並んでいた」「お客様が買ってくれた」という経験が大きな自信や働く喜びを生んでいます。
🔼地域経済の活性化
商品として売れるようになったことで、農家にとっても規格外品が新たな収益源になりました。 さらに販売される加工品は観光客への土産物として人気を集め、地域ブランド力の強化にも貢献しています。
🔼持続可能なSDGsモデル
この協働は「つくる責任、つかう責任(SDG12)」や「働きがいも経済成長も(SDG8)」に該当する取り組みです。企業と福祉が連携することで、持続可能な社会のモデルとして注目されています。
◆課題と今後の方向性
🔼安定供給の難しさ
規格外品の発生量は季節や天候によってばらつきがあるため、加工場に安定的に材料を供給する仕組みが課題となっています。
🔼販路の拡大
直売所や地域イベントだけでなく、全国規模での販路拡大が課題です。特にオンライン販売の強化が期待されています。
🔼加工施設の体制強化
利用者が安全に作業できるためには、衛生管理や品質管理の仕組みをさらに徹底する必要があります。
今後は、地域の他の企業や行政との連携を強化し、原料供給・販路拡大・人材育成を一体的に進めることが求められます。 さらに将来的には、県外の地域でも横展開可能なモデルとして普及していくことが期待されます。
◆まとめ
この協働は、「食品ロス」と「障害者就労支援」という一見全く種類の違う課題を一つの循環の中で解決する画期的な取り組みです。捨てられていたはずの農産物に新たな命を吹き込み、障害者が誇りを持って働く場をつくる。その成果は、地域社会全体をより豊かにし、持続可能な未来を築くための大切な一歩となっています。
この事例は、中小企業がもつ地域密着の強みと柔軟性を活かせば、社会的課題の解決に直結する新しい価値を創造できることを示しています。大企業でなくても、知恵と連携によって大きな成果をあげられるのです。
食品ロス削減と障害者就労支援――この二つの課題を同時に解決する取り組みは、今後の地域共生社会づくりの手本となるでしょう。 そしてそこには、「人も食も、誰一人取り残さない」を実現するための確かな希望が見えていると思います。
◆お知らせ
🔼パーパス経営および具体的CO2削減施策の立案や企業存続のために採用強化や離職防止の施策に悩まれている方、お気軽に無料オンライン
相談をご活用ください。
お悩みや課題をお伺いし、解決策をご提案いたします!!
無料オンライン相談のお申し込みはこちらから
CrowdCalendarクラウドカレンダーとは、Googleカレンダーと連携し日程調整のあらゆる面倒を払拭するWebサービスです。crowd-calendar.com
🔼公式LINE始めました!!お友達募集中!!
最新情報をLINEで配信中!定期的にLINE限定のお得な情報をお送りします。
以下のリンクから公式アカウントを友だち追加できます。
🔼【中小企業対象!27年度大企業に対するサステナ情報開示義務化対応のための新サービス】
※全国対応可能
今すぐ資料請求する今すぐ無料相談を申し込むsasutenabiriti-anketo-nxpaelx.gamma.site