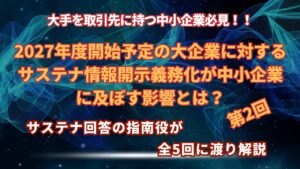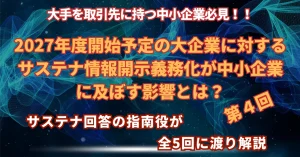第3回中小企業のサステナビリティ情報開示への対応~課題と対策~
◆はじめに
第1回と第2回で、サステナビリティ情報開示の重要性や、国際的な基準について解説してきました。そこで今回は、中小企業がサステナビリティ情報開示に際して直面する課題と、それに対する具体的な対策について詳しく見ていきたいと思います。
◆中小企業が抱える課題
2027年の大企業に対するサステナ情報開示義務化は、大企業だけでなく、中小企業にも大きな影響を与えます。サステナ経営推進における課題として中小企業は、以下の様な課題を抱えていることが多いです。
• コスト負担:
情報収集や開示システムの構築には、多額のコストがかかります。特に、専門のソフトウェア導入やコンサルティング費用は、中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。
• 人材不足:
サステナビリティに関する専門知識を持つ人材が不足しているため、情報収集や分析、報告書作成といった作業を内製することが難しいケースが多いです。
• 情報収集の難しさ:
サステナビリティに関する情報は多岐にわたり、どこから情報を収集すれば良いのか、どのような情報を集めれば良いのかといったノウハウが不足していることがあります。
• 経営資源の制約:
サステナビリティへの取り組みは、経営資源を必要とします。中小企業は、本業の経営に注力せざるを得ない状況で、サステナビリティへの取り組みを後回しにしてしまう傾向があります。
◆中小企業がやるべきこと
中小企業がサステナビリティ情報開示に対応するためには、以下の様な対策を取ることが必要です。
• 早期の準備:
義務化までに十分な時間をかけて、情報収集や体制整備を進めることが重要です。まずは、自社の事業活動が環境や社会に与える影響を把握し、開示すべき情報を特定しましょう。
• 外部の支援を活用:
コンサルタントや専門家、業界団体などの外部の支援を活用することで、効率的に情報収集や体制整備を進めることができます。大企業をメイン顧客とする大手有名コンサルタント会社は高価格となることが多いですが、我々のような比較的低価格で中堅・中小企業への支援を主としてサステナ経営推進支援を行っているコンサルタントを活用することを考えましょう。
• デジタルツールの活用:
サステナビリティに関する情報を管理・分析するためのデジタルツールを活用することで、業務効率化を図ることができます。
• 業界団体との連携:
業界団体が提供する情報やノウハウを活用することで、他の中小企業との情報交換や共同での取り組みを進めることができます。
• 従業員の意識改革:
全従業員がサステナビリティの重要性を理解し、行動に移すことが重要です。そのためには、段階的な(役職別など)サステナ経営推進研修やワークショップを行うのが有効です。ただし、これを実施するためには、自社の明確なサステナ経営方針が定まっていないと意味がありません。つまり、これらを実施する前に、自社のサステナ経営方針と優先課題と目標をあらかじめ設定しておく必要があります。よって、サステナ経営方針、優先課題、目標の設定→全社で取り組むための従業員意識改革の順番となります。
まとめ
中小企業にとって、サステナビリティ情報開示は大きな課題ですが、中小企業がサステナ経営推進に取り組む一番の理由は、取引先である大企業からの取引中止というリスクを回避するということが最優先です。売り上げがいくら伸びるのか?ということも大切ですが、今の売り上げの大きな割合を占める大企業との取引が無くなる方が会社にとっては大きな損失なのです。また、この取り組みを進める過程で、新たなビジネスチャンス(社会課題解決型新規ビジネスや自社の強みと他社の強みを掛け合わせた新たなサービスなど)を生み出す可能性も秘めています。
中小企業は、自社の規模や状況に合わせて、柔軟な対応策を講じる必要がありますが、悩む時間はそう長くは取れません。外部の専門家の支援を積極的に活用し、段階的に取り組みを進めることで、結果的に低コストでサステナビリティ経営を実現することができます。
【次回予告】
次回は、サステナビリティ情報を開示することによって企業が得られる具体的なメリットについてご紹介します。