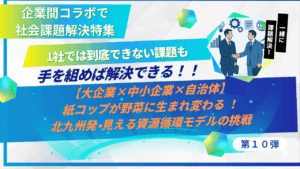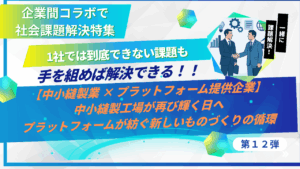「中小企業 × 事業者群 × 自治体」三位一体北九州市発・オフサイト方式食品残渣リサイクルが描く「捨てない街の仕組み」
目次
- ◆はじめに
- ◆参加主体
- ◆コラボレーションの背景
- ◆具体的な取り組み
- ◆啓発と教育の展開
- ◆社会課題解決への効果
- ◆課題と展望
- ◆まとめ
- ◆お知らせ
◆はじめに
食品廃棄物という「見えない課題」
いま、日本では年間約2,500万トンもの食品廃棄物が発生しています(環境省・農林水産省 2023年公表)。そのうち、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」は約464万トンにものぼります。飲食店や食品製造業では、調理過程で出る残渣や食べ残しの処理が日常的な課題です。多くの事業者が焼却処理に頼らざるを得ず、コストと環境負荷の両面で悩みを抱えています。
一方で、地方自治体ではごみ減量化や環境負荷低減を進める必要があります。とくに北九州市は、「環境モデル都市」として早くから循環型社会づくりに力を入れてきました。廃棄物を減らすだけでなく、「地域の中で資源を循環させる仕組み」をどう構築するかが次の課題となっていました。
そんな中で始まったのが、「オフサイト方式食品残渣リサイクル」の取り組みです。これは、市内の飲食店や食品事業者から出る食品残渣を一括で回収し、発酵処理施設で堆肥化。その堆肥を市内の農家に還元して野菜づくりに活用するという、地域ぐるみの資源循環プロジェクトです。
この仕組みの核を担っているのが、北九州市に拠点を置く環境事業会社です。同社は、これまで培ってきた発酵技術と地域連携のノウハウを活かし、「地域全体で食の循環をつくる」ことを目指しました。
◆参加主体
官民が支え合う連携モデル
環境事業会社は、もともと廃棄物のリサイクルや堆肥化処理を手がける中小企業です。北九州市内で長年、一般廃棄物や食品残渣の処理を行うなかで、「処理」から「再資源化」への転換を志向してきました。
このプロジェクトでは、同社が中心となり、市内の飲食店・食品製造業者・ホテルなどが協力店舗として参加しています。各店舗では、厨房から出る野菜くず、食べ残しなどを分別して専用容器に入れます。
さらに、北九州市が制度面・啓発面で強力にバックアップしました。自治体は、環境政策課や循環型社会推進部門が連携し、事業者向け説明会を開催。回収ルートや費用負担の仕組みづくりを調整するなど、行政と民間が一体となって仕組みを整えました。
つまり、この取り組みは「中小企業 × 事業者群 × 自治体」という三位一体の協働によって成り立っています。誰か一社の努力だけでは成し得なかった「地域単位のリサイクル構想」を、複数のプレイヤーが共に担う形で実現しているのです。
◆コラボレーションの背景
個では限界、共で未来をつくる
飲食店が単独で堆肥化に取り組むことは簡単ではありません。設備投資や維持管理のコスト、スペース、そして人手。小規模事業者ほど「やりたいけれどできない」現実がありました。
環境事業会社が着目したのは、「オフサイト方式」という考え方です。これは、店舗や工場内で処理する「オンサイト方式」に対して、発生した残渣を外部の施設で一括処理する方法です。各店舗は分別だけを担い、専門事業者が回収・処理を行うため、効率的かつ衛生的に運用できます。
この仕組みなら、参加する事業者の規模を問わず取り組める――そう考えた同社は、自治体に協働を打診。市の環境部門も「ごみ減量」と「リサイクル推進」の双方に寄与することから前向きに応じました。
結果的に、この構想は北九州市のごみ減量モデル事業として位置づけられ、市と民間が協働するかたちで制度化。官民の信頼関係を土台に、2018年4月より一部事業化が始まり、2025年4月より本格運用がスタートしています。
◆具体的な取り組み
回収から農業への循環まで
🔼回収・分別の段階
プロジェクトに参加する飲食店や食品事業者は、厨房内で出る食品残渣を専用容器に分別します。生ごみや残飯、調理くずなどは、金属・プラスチックが混ざらないよう注意しながら回収します。
環境事業会社は、専用トラックで各店舗を定期巡回。市の支援を受けて効率的なルート設計を行い、燃料コストやCO₂排出も抑えています。
🔼発酵処理・堆肥化の段階
集められた食品残渣は、同社の発酵処理施設に運ばれます。ここでは独自の低温発酵技術を用い、微生物の力で残渣を分解。短期間で高品質な堆肥へと生まれ変わります。
処理過程では臭気対策や衛生管理も徹底され、都市部近郊でも安心して稼働できる環境づくりがされています。この技術は、環境省の「地域循環共生圏」の考え方にも通じるものです。
🔼農業活用・地域還元の段階
完成した堆肥は、市内および近郊の農家に供給されます。これにより、農家は安定的に有機肥料を確保でき、化学肥料への依存を減らすことが可能になります。
農家で育った野菜は、やがて市内の飲食店に戻り、再び食卓に並びます。こうして「食べる → 捨てる → 肥やす → 育てる → また食べる」という循環が、地域の中で完結するのです。
◆啓発と教育の展開
この仕組みを広げるため、環境事業会社と市は学校や企業向けの環境学習を実施しています。リサイクル施設の見学や出前授業を通じて、市民が自らの食と廃棄の関係を実感できるよう工夫されています。
◆社会課題解決への効果
廃棄物が「地域資源」に変わる瞬間
この取り組みの成果は、単なる廃棄物処理の効率化にとどまりません。
まず、飲食店や食品業者のコスト削減につながりました。従来の焼却処理に比べ、重量の軽減や処理頻度の最適化により、経済的な負担が減ります。
また、温室効果ガスの削減効果も見逃せません。焼却処理を減らすことでCO₂排出を抑制し、カーボンニュートラルの一助となっています。
さらに、地域農業の支援という副次的効果もあります。堆肥の利用が進むことで、農家はコストを抑えつつ環境負荷の少ない農業を実践できます。実際、北九州市の一部農家ではこの堆肥を使った野菜づくりが始まり、「地元で食べる喜び」が新しいブランド価値を生んでいます。
こうした「見える循環」は、市民の意識変革にもつながっています。廃棄物を“処理するもの”から“循環させる資源”へ。その発想転換を、北九州のまち全体が体現しつつあるのです。
◆課題と展望
広げるための次の一歩
最大のハードルは、運搬コストと効率化です。オフサイト方式は衛生的で柔軟な反面、広域化すると輸送費が増大します。環境事業会社では、回収エリアの最適化や車両の省エネ化を進めながら、この課題解決を模索しています。
また、参加事業者の拡大には、継続的な啓発活動が欠かせません。分別の徹底や、堆肥化の意義を理解してもらうことが、取り組みの安定運営に直結します。
さらに、堆肥の品質管理と販路開拓も重要なテーマです。農家にとって使いやすい堆肥を安定的に供給することが、地域循環の信頼性を高める鍵となります。
今後は、このモデルを他地域に広げることも視野に入っています。地方都市の多くが同じような課題を抱える中で、北九州モデルは「中小企業が中心となる官民連携スキーム」として注目されています。
◆まとめ
共創がつくる地域循環の未来
北九州市のオフサイト方式食品残渣リサイクルは、単なる環境施策ではありません。それは、中小企業の技術力と地域ネットワーク、自治体の政策支援、事業者の協力が有機的に結びついた「共創のエコシステム」です。
環境事業会社の担当者は、「地域の力を信じて、人と資源の流れをつなげたい」と語ります。その言葉通り、ここには“技術”だけでなく、“信頼”と“共感”によって動く仕組みがあります。
食べる人、作る人、支える人。そのすべてが関わるこの循環は、「地域が自らの手で未来をつくる」象徴的なモデルです。
北九州市が築いたこの小さな循環は、やがて全国の地域社会が抱える大きな課題を解くヒントになるかもしれません。
◆お知らせ
🔼パーパス経営および具体的CO2削減施策の立案や企業存続のために採用強化や離職防止の施策に悩まれている方、お気軽に無料オンライン
相談をご活用ください。
お悩みや課題をお伺いし、解決策をご提案いたします!!
無料オンライン相談のお申し込みはこちらから
CrowdCalendarクラウドカレンダーとは、Googleカレンダーと連携し日程調整のあらゆる面倒を払拭するWebサービスです。crowd-calendar.com
🔼公式LINE始めました!!お友達募集中!!
最新情報をLINEで配信中!定期的にLINE限定のお得な情報をお送りします。
以下のリンクから公式アカウントを友だち追加できます。
🔼【中小企業対象!27年度大企業に対するサステナ情報開示義務化対応のための新サービス】
※全国対応可能
今すぐ資料請求する今すぐ無料相談を申し込むsasutenabiriti-anketo-nxpaelx.gamma.site